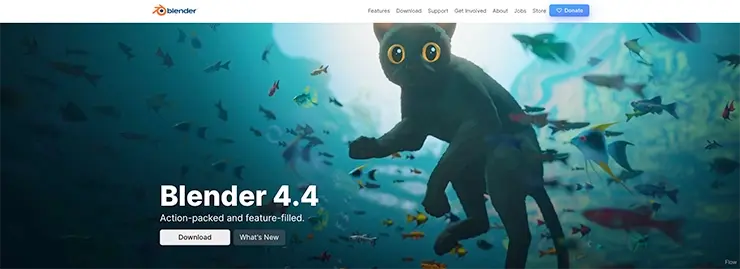Blenderとは?| 機能を詳細解説
- KIMURA Tetsuya
- 2025年7月12日
- 読了時間: 7分

Blenderは、3DCGクリエイターの間で広く知られるオープンソースの3D制作ソフトウェアです。モデリング、アニメーション、レンダリング、さらにはVFXや動画編集まで対応できる多機能さと、無料で使えるという大きな魅力から、世界中のクリエイターに選ばれています。
この記事では、そんなBlenderの特徴や価格、他の代表的な3DCGソフトとの違い、搭載されている主な機能について詳しく解説します。さらに、Blenderがどのような作品制作で活用されているのか、その可能性や活用シーンも紹介していきます。
Blenderのダウンロード方法や初期設定については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
Blenderとは?
Blenderは、無料で使えるオープンソースの3Dコンテンツ制作ソフトウェアです。個人クリエイターからプロの現場まで幅広く利用されており、映画やアニメーション、ゲーム開発、
さらにはプロダクトデザインやVFXの分野でも活躍しています。
ノードベースで柔軟性の高いインターフェースと、強力な3Dモデリング、アニメーション、物理シミュレーション、レンダリング機能を備えており、これ一つで3DCG制作のほとんどを完結させることができます。
Blenderの価格
Blenderは、公式にオープンソースとして提供されており、個人・商用を問わず無料で利用できる3D制作ソフトウェアです。ライセンス上の制限もなく、誰でも自由にダウンロードして使うことができます。
高機能な3DCGツールが無償で公開されていることで、これまで商用ソフトの高額なライセンス費用が障壁だったクリエイターやスタジオにとって、Blenderは非常に魅力的な選択肢となっています。世界中の多くのプロジェクトで採用されている理由のひとつが、この「高性能でありながら無料」という大きな特徴です。
Mayaとの違い
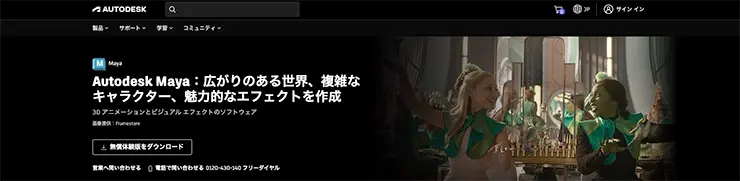
BlenderとAutodesk Mayaは、どちらも3DCG制作において高い評価を受けているツールですが、ライセンス形態や得意分野、操作性に明確な違いがあります。
Blenderはオープンソースで無料提供されており、誰でも自由にダウンロードして利用できます。一方、Mayaは商用ソフトウェアで、サブスクリプション契約による有料ライセンスが必要です。
また、インターフェースや操作感にも違いがあり、Blenderはオープンソースならではのカスタマイズ性と軽快さ、Mayaは映画・VFX業界標準の高い拡張性やパイプライン統合力が魅力です。最適な選択は、目的や制作環境、求める機能によって変わってきます。
比較項目 | Blender | Autodesk Maya |
価格・ライセンス | 無料(オープンソース、商用利用可) | 有料(サブスクリプション契約が必要) |
得意分野 | モデリング全般、個人・小規模制作 | キャラクターアニメーション、VFX、大規模制作 |
拡張性・カスタマイズ | 高い(オープンソースならではの自由度) | 非常に高い(スクリプト・パイプライン統合向き) |
導入ハードル | 低い(誰でも自由に導入可能) | 比較的高い(ライセンス契約・費用が必要) |
Blenderの特徴
Blenderは、無料でありながらプロフェッショナルレベルの3DCG制作が可能なソフトとして、多くのクリエイターに選ばれています。その魅力は多岐にわたりますが、特に注目すべき特徴をいくつかご紹介します。
オープンソースで自由度が高い
Blenderはオープンソースソフトウェアで、誰でも無償で利用できるだけでなく、ソースコードにアクセスしてカスタマイズすることが可能です。これにより、独自の機能追加やパイプラインへの統合など、柔軟な活用ができます。
クロスプラットフォーム対応
Windows、macOS、Linuxといった主要なプラットフォームで動作するため、環境を選ばず導入しやすいのも大きな魅力です。個人制作からチーム制作まで幅広い場面で活用されています。
豊富で統合された機能群
モデリング、スカルプティング、アニメーション、レンダリング、コンポジット、さらにはVFXや動画編集まで、3DCG制作に必要な機能が一通り揃っています。別ソフトを行き来する必要がなく、Blenderだけで完結できる制作フローを実現できます。
Blenderでできること
Blenderはその多機能さとオープンソースの特徴から、3DCG制作のあらゆる場面で活用されています。ここでは主な利用分野と、実際の活用例を紹介します。
レンダリング

引用:Blender公式サイトより
Blenderには高度なレンダリングエンジン「Cycles」と、リアルタイムプレビューに適した「Eevee」が標準搭載されています。これにより、フォトリアルな映像やデザインビジュアルを、高速かつ精度高く生成できる点が強みです。建築ビジュアライゼーションや広告制作、映画・CGアニメーションなど幅広い用途で重宝されています。
モデリング

引用:Blender公式サイトより
Blenderは、頂点・エッジ・面を直接操作できる基本的なポリゴンモデリングに加え、スカルプティング、モディファイヤ、スプライン編集など、多彩な手法を備えています。そのため、精緻なプロダクトデザインから有機的なキャラクターモデリングまで幅広い制作に適しています。
VFX(視覚効果)

引用:Blender公式サイトより
Blenderは、煙・火・布・液体シミュレーションなどのダイナミクス機能と、ノードベースのコンポジッターを統合しています。そのため、映画や広告のVFX制作においても十分な表現力を持ち、外部ソフトを越える総合力を備えています。
アニメーション

引用:Blender公式サイトより
キーフレームベースのアニメーションはもちろん、アーマチュアリギング、Inverse Kinematics、Grease Pencilなどの2D/3D統合表現が可能です。キャラクターアニメからモーショングラフィックスまで幅広く対応します。
最新キービジュアルにも採用されたエピソード
2024年、Blender公式のキービジュアルとなった「Flow」は、Blenderのみで制作されたアニメーション映画です。グラデーション豊かな水面表現やライティングを通じて、Blenderの総合力が公式に「作品」として認められた象徴的な事例と言えます。
Blenderは、映画、ゲーム、アニメ、建築、VFXに至るまで、あらゆるクリエイティブフィールドで信頼されてきました。自由なライセンスと一体型の制作フローにより、個人からプロまで幅広く活用されるツールであることがよく分かる活用例です。
Blenderのデメリット
Blenderは高機能で自由度の高い3DCGソフトですが、他の商用ツールと比べたときに注意すべき点もあります。
まず、機能が非常に豊富である反面、初めて使う場合はインターフェースや操作体系に慣れるまで時間がかかることがあります。特に、他の3Dソフトから移行する場合は、独自の操作感やショートカットに戸惑うことがあるでしょう。
また、オープンソースのため、商用ツールのような公式サポート体制や専用のテクニカルサポートは用意されていません。そのため、トラブル対応や疑問点の解消は、コミュニティフォーラムやドキュメント、オンラインチュートリアルに頼ることが多くなります。
とはいえ、近年はBlenderの学習コンテンツやユーザーコミュニティも世界的に充実しており、積極的に情報収集することでこれらのデメリットは十分に補えるようになっています。
Blenderの将来性
Blenderは、オープンソースプロジェクトでありながら、世界中のユーザーや開発者の支援を受けて今も進化を続けています。定期的なバージョンアップにより、新しい機能の追加やパフォーマンス改善が積極的に行われており、プロフェッショナルの制作現場でも選ばれるツールとしての地位を確立しています。
今後も3DCG業界の技術進化やクリエイターのニーズに応えながら、さらなる可能性を広げていくことが期待されています。
まとめ

Blenderは、無料で使えるオープンソースの3Dコンテンツ制作ソフトとして、多くのクリエイターに選ばれてきました。モデリング、アニメーション、レンダリング、VFXまで統合された豊富な機能と、柔軟なカスタマイズ性がその魅力です。
これから3DCG制作に挑戦する方はもちろん、プロフェッショナルの現場においても、Blenderは十分に注目に値する強力なツールです。目的やスタイルに合わせて、ぜひその可能性を体感してみてください。
Blenderのダウンロード方法や初期設定については、こちらの記事もあわせてご覧ください。