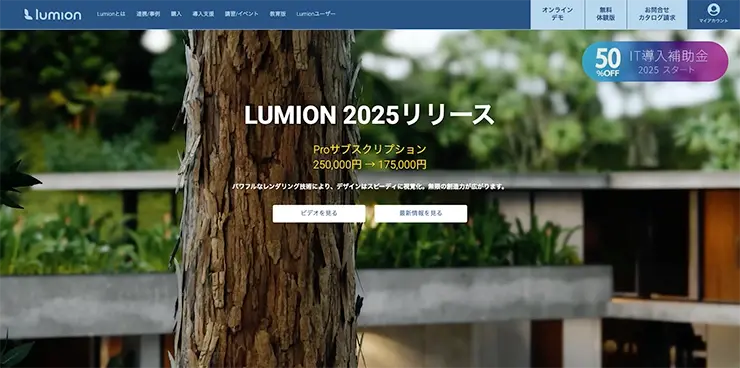【初心者必見】建築パースの作り方完全ガイド|モデリングからレタッチまで簡単解説!
- KIMURA Tetsuya
- 7月12日
- 読了時間: 11分

建築パース(建築CG)は、建物の完成イメージを視覚的に伝えるための3DCG技術で、建築設計の提案・プレゼンテーション・販促資料などに広く活用されています。
以前は専門的な知識や高価なソフトが必要とされていましたが、近年は直感的に操作できるモデリングツールやリアルな質感を自動生成できるレンダリングエンジンが登場し、初心者でも建築パース制作にチャレンジしやすくなりました。
とはいえ、いざ始めてみようと思っても、
「どんなソフトを使えばいいの?」
「モデリングとレンダリングって何が違うの?」
と、疑問や不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、建築パース制作の基本となる「モデリング」「レンダリング」「レタッチ」の3つのステップを、初心者にもわかりやすく順を追って解説します。
また、各ステップでよく使われるツールや操作のコツも紹介しますので、これから建築パースに挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。
建築パース制作の基本ステップとは?
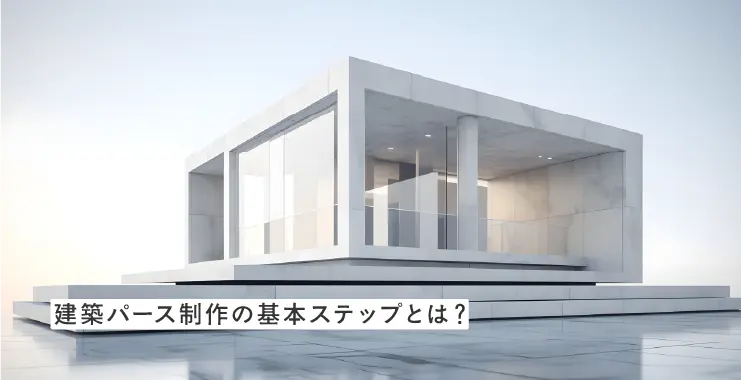
建築パースの制作は、大きく分けて以下の3ステップで構成されます。
モデリング(3Dモデルの作成)
レンダリング(質感・照明の設定と画像出力)
レタッチ(仕上げの画像編集)
それぞれの工程は連続しており、段階を追って進めることで、建物の完成イメージをリアルに、かつ効果的に表現できます。
まず全体の流れを理解した上で、各工程の目的と役割について簡単に把握していきましょう。
モデリング|建物の形状を3Dで設計する

建築パースの制作において、最初のステップとなるのが「モデリング」です。これは、設計図や写真などの資料をもとに、建物や空間の立体的な構造を3D空間上で再現する工程を指します。
平面図やアイディアを、視覚的にわかる「かたち」に落とし込む作業ともいえるため、非常に重要なフェーズです。
モデリングの基本手順
モデリングの基本的な手順は以下の通りです。
STEP.1 データ収集と構想設計
まずは、建築図面・スケッチ・写真資料などの素材を集めることから始めます。
そうした素材をもとに、建物の構成・スタイル・見せたいポイント(正面・側面・上部など)を整理します。設計意図や用途に合わせて、「どの部分に力を入れるか」「どの視点で見せるか」などの構想を固めることが大切です。
例:商業施設ならファサード(正面)重視/住宅なら外観と庭の調和が重要 など
STEP.2 モデリングソフトの選定
いきなりプロ向けソフトに挑戦するより、まずは自分の思い描く形を作ることを目的にした方が、習得がスムーズになります。
STEP.3 建物の形状を作成
ソフトが決まったら、基本図形(プリミティブ)を使って建物の骨組みを作成します。立方体や円柱などを組み合わせて、外壁・屋根・柱などの大枠を設計。ここではまだ詳細にこだわらず、「全体のバランス感」を確認する段階です。
STEP.4 ディテール追加
建物の大まかな形が完成したら、細部のディテールを加えてリアルさを強化していきます。
窓、扉、バルコニー、屋根、階段などの建築的な要素を追加することで、現実の建築に近づけていきます。
よく使われるモデリングソフト(初心者向け)
SketchUp
SketchUpは建築・インテリア・都市設計など、プロから初心者まで広く支持されている3Dモデリングソフト。
特に建築パースの初学者に人気があり、操作がシンプルでとっつきやすく、ドラッグ&ドロップや「プッシュ/プル」機能など、直感的なUIが特徴です。
3D素材ライブラリ「3D Warehouse」も活用でき、家具や窓などの配置もすばやく行えます。チュートリアルも充実しており、初めての3Dでも安心して学べます。
料金:無料プランあり(有料プランは年額)
学習コスト:低め(日本語の解説多数)
こんな人におすすめ:建築パース初心者/設計やレイアウトを短時間で形にしたい人
TinkerCAD
TinkerCAD(ティンカーキャド)は、Autodesk社が提供する初心者向けの3Dモデリングツール。ブラウザ上で動作し、インストール不要で気軽に始められる点が最大の魅力です。
もともと教育現場での使用を想定して設計されており、子どもでも扱える直感的な操作性が特徴。ブロックのように形状を組み合わせてモデリングするスタイルなので、複雑な造形よりも、簡単な形状を使った建築パースの基礎学習に向いています。
料金:完全無料
学習コスト:非常に低い(公式チュートリアルあり)
こんな人におすすめ:これからモデリングを学びたい初心者/ソフトの操作に慣れていない人/ブラウザだけで気軽に試したい人
レンダリング|リアルな質感と光で見せる

レンダリングとは、モデリングで作成した3Dデータに対して、質感(マテリアル)や光(ライティング)を設定し、リアルな完成イメージに仕上げる工程です。言い換えると、立体の「枠組み」に、現実らしさを与える仕上げ作業ともいえます。
完成イメージを可視化するうえで非常に重要な工程であり、建築パースの魅力や説得力を左右するパートです。
レンダリングの基本手順
STEP.1 照明の設定(ライティング)
最初に行うのが、光源の設定です。たとえば、昼間の外観パースなら太陽光の角度や強さ、夕方ならオレンジがかった光の演出、室内なら間接照明やスポットライトなどを追加します。
光の当て方ひとつで、建物の印象は大きく変化します。「陰影がつくことで立体感が増す」「柔らかい光で温かみを演出する」など、建物の魅力を引き出す光をどう設計するかがポイントです。
STEP.2 材質(マテリアル)の設定
次に行うのは、建物の各パーツに現実の素材感を与える作業です。
外壁 → コンクリート、レンガ、タイルなど
窓 → ガラス、金属フレーム
床 → 木材、石材、カーペット
質感の設定では、「反射」「光沢」「ザラつき感」「透過性」などを細かく調整できるソフトも多く、リアルさの鍵を握ります。
例:ガラスの透明感、木材の年輪、金属のツヤなど
初心者の場合は、ソフトに内蔵されたプリセット(既製マテリアル)を活用するのが効率的です。
STEP.3 カメラアングルの調整
質感と光の設定が完了したら、どの視点から建物を見せるか(構図)を決めるカメラ設定に入ります。
正面から全体を見せる
少し斜めに振って奥行きを出す
視点を下げて迫力を出す など
さらに、焦点距離(ズームの度合い)や被写界深度(背景のボケ感)を調整することで、まるで一眼レフで撮影したような演出が可能になります。
建築パースのアングル決め方に関連する詳しい解説は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
レンダリングに使用されるソフトの例
V-Ray

V-Rayは、建築ビジュアライゼーションのプロ現場で定番の高品質レンダリングソフト。リアルな光の反射や素材表現に優れており、リアリティのある建築パースを求めるユーザーに最適。
SketchUpやBlender、3ds Maxなど多くの3Dソフトに対応したプラグインとしても利用でき、ワークフローに柔軟に組み込めます。
料金:有料(年間サブスク制/30日間体験版あり)
学習コスト:中程度(基礎操作は動画解説が充実)
こんな人におすすめ:高品質な建築パースを制作したい人/プロ仕様のツールを使いたい人
Lumion
Lumionは、建築向けに特化したリアルタイムレンダリングソフト。素材や光、環境効果(雨・風・季節など)のプリセットが充実しており、操作も直感的。短時間でフォトリアルなビジュアルを作成できるのが大きな魅力です。
建築プレゼンや動画出力にも強く、クライアント提出用の高品質なアウトプットに適しています。
料金:有料(年間ライセンス制)
学習コスト:中(UIは親しみやすい)
こんな人におすすめ:設計ビジュアルを素早く仕上げたい人/パース作成からプレゼン動画までを一括管理したい人
レタッチ|画像を整え、見せ方を仕上げる最終工程

レタッチとは、レンダリングで出力した画像に対して色味の調整や不要物の除去、演出の追加などを行い、完成度と訴求力を高める仕上げ作業です。
建築パースは「設計の意図を伝えるビジュアル」である以上、ただリアルなだけでなく、伝えたい雰囲気や印象を的確に表現することが求められます。最終段階にレタッチをすることで「魅せ方の調整」を行うことで、提案力のある建築パースに仕上がります。
レタッチの基本手順
STEP.1 色調補正
まず行うのは、画像全体の色味や明るさを整える作業です。
明るさ(Brightness)やコントラスト(Contrast)を調整してメリハリをつける
彩度(Saturation)を調整して色味の印象を強調・緩和する
カラーバランスを変えて、朝・昼・夕方など時間帯の雰囲気を演出する
こうした色調補正は、Adobe PhotoshopやLightroomなどの画像編集ソフトで簡単に行えます。初心者は「プリセット(カラールックアップ)」を活用することで、ワンクリックで印象を変えることも可能です。
カラールックアップについては、こちらの関連記事で詳しく紹介しています。
STEP.2 不要な要素の除去
レンダリング後の画像には、以下のような「微妙な違和感」や「ノイズ」が残ることがあります。
モデルの重なりで生じた不自然な影
空に出たノイズやぼやけ
窓の反射や床の反りなど、微妙なゆがみ
これらを修正ツール(スタンプ、修復ブラシ、コンテンツに応じた塗りつぶしなど)で取り除くことで、違和感のない自然な画像に近づけます。
特にプレゼン資料に使う場合は、「気になる箇所を1つずつ整える丁寧さ」が完成度を左右します。
STEP.3 合成・演出
最後に、必要に応じて要素の追加や演出を行います。
空をドラマチックな夕景に変更する
植栽や人物(スケール感)を合成する
商業施設なら人の流れや看板などを追加して「用途」を強調する
窓に光を入れて時間帯の印象を明確にする
これらは、リアルさよりも「見せたい印象」「伝えたいストーリー」を優先する演出として効果的です。
特にPhotoshopでは、選択範囲やマスク機能、レイヤーの合成モードを活用することで、自然な合成が可能になります。
レタッチに使用されるソフトの例
Adobe Photoshop
Adobe Photoshopは言わずと知れた画像編集の定番ソフト。建築パースの最終調整やレタッチ、空の差し替えや雰囲気作りに幅広く使用されます。マスクやレイヤー、カラールックアップ、ぼかし、合成などの多機能を駆使することで、レンダリング後の完成度を大きく引き上げることができます。AI機能も強化され、選択や塗りつぶしがより直感的に。
料金:サブスクリプション制(Adobe CC単体プランまたはフォトプラン)
学習コスト:中(基本操作の習得は簡単だが、応用機能が多いため継続学習が必要)
こんな人におすすめ:建築パースの仕上げを丁寧に行いたい人/光や空気感を調整したい人
Adobe Lightroom

Adobe Lightroomは、主に写真の現像や色調整に特化したAdobe製ソフト。Photoshopと異なり、非破壊編集が可能で、色や明るさ、コントラスト、ホワイトバランスの微調整が得意です。レタッチというより“仕上げの色調補正”に向いており、簡単な操作で画面全体の印象を変えることができます。
料金:サブスクリプション制(Photoshopとのセットプランあり)
学習コスト:低(UIがシンプルで初心者でも扱いやすい)
こんな人におすすめ:色補正を効率よく行いたい人/写真寄りの作風を好む人
生成AIツールの活用でレタッチをもっと手軽に

最近では、DALL·EやFireflyといった画像生成AIや、Photoshopに統合された生成AI機能を使うことで、空の差し替え・天候エフェクトの追加・時間帯の変更などを簡単に行えるようになっています。従来はPhotoshop上で手動合成やマスキングが必要だった作業も、プロンプトを入力するだけで自然な結果が得られるため、初心者でも直感的に操作でき、作業時間の短縮にもつながります。
よく使用される生成AIツールの例
DALL·E / Firefly(ダリー・ファイアフライ)
いずれも画像生成AIツール。DALL·EはOpenAI提供、FireflyはAdobe製。建築パースでは背景の合成や空の生成、天候エフェクト(雨・雪など)作成に活用されます。素材写真を探す代わりに、生成AIで必要な要素を直接作り出すことで、作業効率が大幅に向上します。特にFireflyはAdobe Stockベースの安全な素材生成が強みで、Photoshopとの相性も抜群です。
料金:DALL·Eは一部無料(OpenAI経由)、FireflyはAdobe CC契約者向けに提供
学習コスト:中(プロンプトの工夫が必要)
こんな人におすすめ:天候・背景合成に手間をかけたくない人/Photoshopとの連携を重視する人
DALL·E3に関連する詳しい解説は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
Photoshop 生成AI機能
Adobe Photoshopに統合された生成AI機能。コンテキストタスクバーを使って、画像内の選択範囲に自然な背景・エフェクト・素材を“生成”してくれる革新的な機能です。空の差し替え、芝生の雪化、建物の時間帯変更(夕景→夜景など)といった工程も、プロンプトを入力するだけで完了できます。複雑なマスクや手動合成が不要になるため、初心者の時短にも最適です。
料金:PhotoshopのCreative Cloud契約に含まれる(生成回数に制限あり)
学習コスト:低〜中(UIはシンプルだが、プロンプト設計力が鍵)
こんな人におすすめ:AIの力で仕上げを効率化したい人/マスクや合成が苦手な初心者
建築向け画像生成AIに関連する詳しい解説は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
まとめ

建築パースの制作には、モデリング→レンダリング→レタッチという3つの主要ステップがあります。それぞれに異なるスキルとツールが求められますが、段階を追って学ぶことで、初心者でも十分にクオリティの高い作品を仕上げることができます。
まずはシンプルな建物から始めて、少しずつ素材やライティング、演出の幅を広げていくことが上達への近道です。特に、無料ソフトやテンプレートの活用、Photoshopでの補正技術を身につけることで、見違えるほど完成度が高くなります。
これから建築パース制作に取り組む方は、ぜひ今回のガイドを参考に、実際に手を動かして試してみてください。